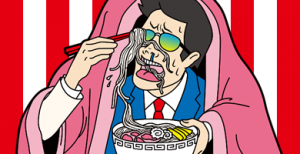絶対に失敗しない!忘年会の司会術
挨拶や自己紹介は簡潔、そして元気に!

忘年会の盛り上がりやスムーズな進行は司会者次第!
忘年会の司会、というといつもの飲み会とは違って緊張度もググッと上がる。忘年会には会社の社長や役員などのお偉いさんをはじめ、取引先や仕入れ先など普段のメンバーとは違う人が参加するからだ。
ここで失敗したら、しばらくみんなの笑い者。
そうならないためにも、司会進行の「ツボ」を抑えておきたい。
まずは簡潔に自己紹介
まず司会者として、自己紹介は大切だ。
これは「皆様、本日は一年の締めくくりとなる忘年会に出席いただきましてありがとうございます。
本日の司会進行役を務めます、○○課の○○と申します。どうぞ宜しくお願いいたします」程度にとどめ、簡潔に終わっておきたい。
長々と自己紹介をすると、それだけで座が白けるおそれもあるし、また乾杯を心待ちにしている人も多いからだ。
参考:失敗しない忘年会の挨拶事例
お偉いさんの挨拶では気配りを
次に、社長や役員の挨拶だが、これは挨拶が終わるたびに「○○部長、ありがとうございました!」と必ずお礼をのべること。
ここで注意しておきたいのは、挨拶をしてくれる人や乾杯の音頭を取る人の肩書き、名前を絶対に間違えないことだ。
小さなノートや単語帳を使い、プログラムの順番に名前を記入しておく。あるいは忘年会の進行表に書き加えておくなどして間違えない工夫をしておくのがベター。
また、閉会の挨拶の時によくあるのが、飲み過ぎて自分の出番を忘れてしまう人。
プログラム通りにスムーズに進めるためにも、司会者として常に全体を見渡して、出番が近づいた人には小声でお願いをしておくなどの気配りが必要だ。
乾杯を元気に盛り上げよう!
乾杯の時は、ひときわ元気よく紹介したい。
「それでは乾杯に移りたいと思います。乾杯の発声は○○さんにお願いしたいと思います。○○さん、こちらへどうぞ!」と大きな声で盛り上げる。
もし、乾杯の挨拶をお偉いさんではなく、その年に活躍した人などにお願いした場合は「それでは乾杯の音頭は、今年○○で見事○○賞を取られた時の人、○○課の○○さんにお願いします!○○さん、一言ご挨拶と乾杯の音頭をお願いします!」と紹介してもいい。
乾杯は忘年会のプログラムの中でも特に大切だからこそ、司会者ははずさないように元気よくいきたいもの。
要所要所の挨拶は大事だ
食事に入る前も一言、「それでは皆さん、まずはお料理やお酒、ご歓談をお楽しみください。後ほど余興に移らせていただきます」と挨拶を。
要所要所に挨拶を入れることで、参加者は「あ、これから食事なんだ」「もうすぐ余興が始まるんだ」と区切りがわかり、忘年会全体もスムーズに進行する。
司会者のつっこみは盛り上がる!
余興やゲームは、司会者は漫才でいうところの「つっこみ」役。
「おっ!○○さん、さすが仕事同様、ゲームも回転が速い!」「豪華賞品ゲットといえば○○さんが活躍しないわけがないです!」「まるでアイドル並みの○○さんの歌とダンスに注目!」などと賑やかな言葉をはさみながら、どんどん盛り上げていこう。
余興が盛り上がるか盛り上がらないか、こうした余興が盛り上がるか否かは、司会者の話術ひとつにかかっているといっても過言ではない。
このようなウケる話術をモノにするには、自分が「この人の司会、おもしろいな」と思った芸能人やお笑い芸人に学ぶのがベスト。
気になる司会者がいたら、忘年会の前にビデオで勉強しておくこともおすすめだ。
締めの挨拶も簡潔に
さて、宴もたけなわだが忘年会にも終わりがある。
最後は、「さて忘年会もそろそろお開きの時間です。最後にここで○○さんに三本締めの音頭をいただきます」などと、簡潔に締めるようにしたい。お酒が入っている上にダラダラと長く続く挨拶では、せっかく盛り上がった忘年会も白けてしまうからだ。二次会があるならその案内もお忘れなく。
時間がもし押してしまうようなら、余興や歓談を5分ほど早めに切り上げるのが良い。
忘年会が終わってからもダラダラと店の入り口付近でたむろしている人をよく見るが、あれは店側にとっても迷惑。時間通り切り上げて次へ進めるよう、幹事とともに司会者も「気配り」を忘れずに。